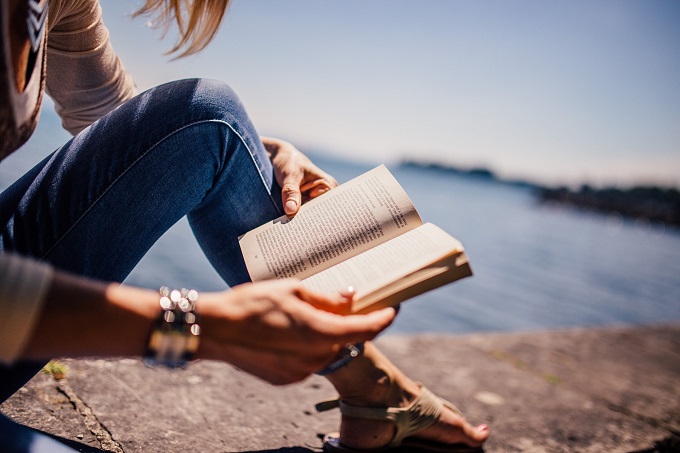辛かったテスト期間が終わり、いよいよ夏休みがはじまりました!
高校生にもなると夏休みは部活で仲間と一緒に汗を流したり、好きなことのためにバイトをがんばったりと人それぞれの過ごし方があると思います。
高校時代の私はラグビー部のマネージャーをしていたため、部員さんに負けないくらい真っ黒になりながら物品を運んだり、ウォータークーラーの飲み水をバケツに溜めたりと忙しい毎日を過ごしていました(笑)
毎年合宿にも参加していたので、今思えば“青春していたな~”の一言につきます(*^^*)
そんな想い出いっぱいの夏休みですが、高校生になり科目数が増えたことで“宿題”の数は恐ろしいことに…(+_+)
限られた時間のなかでプリントや問題集をやるだけでも手一杯なのに、なぜいま“詩”を作らせる!?と思ったことはありませんか?(笑)
この記事を読んでくださっているあなたは、きっとそう思っている人だと思います。
そこでそんなあなたの悩みを少しでも解決するために、ここでは「詩」の攻略法について紹介させていただきます!
「詩」というと学校の教科書で読み、その内容について詳しくみていくことが多いと思いますが、“こうだ!”という定義もなく、わかりにくい存在ですよね。それを自分が書くとなると手の付け方がわからず困ってしまうものです・・・。
だけど大丈夫です!ここでお伝えするちょっとしたポイントをおさえるだけで、あなたも素敵な詩をつくることができますよ♪
夏休みの詩の宿題攻略法!「詩」とは?何を書けばいいの?ルールは?
「詩」といえば小学生のときから国語で勉強しますが、作品によって雰囲気が180度違ったりしますよね。
今ではあまり馴染みのない昔の言葉で書かれているものや、内容よりはリズムを楽しむものなど、“どっちも「詩」なの?”という疑問すら出てくるくらい・・・(+_+)
そのため書けといわれても、どのように書けば宿題としての「詩」になるのか迷ってしまいますよね?
詩を作るには、まず詩について知ることが1番の近道です。ここでは簡単に詩の基本的な知識についてお伝えしていきますね!
詩ってなに?
「詩」は簡単にいうと、言葉の組み合わせによる文学作品です。そして内容によっていくつかのジャンルに分類されているため、同じ「詩」というジャンルであっても作品によって受ける印象が全く異なってくるのです。
ここでは簡単に詩の種類についてまとめてみますね。
① 言葉の違い
・口語詩:現代の言葉を使って作られた詩
・文語詩:昔の言葉を使って作られた詩
② 形式の違い
・定型詩:使用する音数に一定の決まりがあるもの
・自由詩:特に音数のきまりがないもの
・散文詩:短い言葉で改行せず、通常の文章(散文)で書かれるもの
③ 内容の違い
・叙情詩:作り手の感動を中心とした詩
・叙景詩:見たものをありのままに描写した詩
・叙事詩:歴史を中心とした詩
このように言葉・形式・内容の違いのなかでも、さらに分類することができ、組み合わせ次第では色んなタイプの詩が存在することになります。そのため「詩」そのもののイメージがつかみにくいことも、実は無理がない話なのです(+_+)
しかし見方を変えてみると「詩」を作るために大きな決まりごとはなく、自分の思うままに作るだけで簡単に「詩」として成立するということにもなります!
ただし高校生にもなってくると詩の形式が指定されている場合もあると思います。自由に書くのと違って少し取っつきにくいかもしれませんが、そんなときはこれらの内容を頭に入れ、参考にしていただければと思います♪
詩の作りかた
詩を作ることが難しくないということがわかったところで、いよいよ作り方についてお伝えしますね(*^^*)
① 書く内容(テーマ)を決める
“これについて書いてみようかな”と思えることをイメージし、紙に書いてみましょう。
せっかくなので夏休みに経験したことを選んでみてください。記憶にも新しいですし、書きやすいと思います!
② テーマに関係する言葉(キーワード)を考える
例えば「部活」をテーマにした場合、「グラウンド」「汗」「太陽」「仲間」など、「夏祭り」から想像できる言葉を思いつくだけ書き出してみましょう。
③ キーワードを含んだ短い文章を作る
こちらも例をあげてみると
・「グラウンド」では部活をしている
・「汗」が光る
・「太陽」がまぶしい
・かけがえのない「仲間」ができた
のように、体験したことを簡単な文章にしてみましょう。
④ 作った文章をまとめる
作った文章の順序を入れ替えたり、つなぎとなる文章を追加しながら、1つの物語になるようにまとめてみましょう。
「部活」
まばゆい光に目を細めると
強い日差しが私の白い肌を射す
グラウンドを見渡せば
ボールを追いかけ地を駆け回る生徒たち
熱気を帯びたその姿で
夏の暑さを吹き飛ばし
キラキラと光る汗が
彼らの額に伝う
いつの日か思い出すのだろうか?
今この瞬間を
いつの日か思い出すのだろうか?
大切な仲間と過ごした夏を
いつまでも忘れることなく
思い出話にできるように
いつまでも忘れない
仲間と過ごした青春を
というような感じでテーマを決めてキーワードを出し、文章を作って組み合わせるだけで、それらしい作品が完成します!
ちなみにこの作品は私が今思い付きで作っただけなので、いろんな感想があると思いますが温かい目で見守ってください(笑)
夏休みに体験したことをテーマにすれば、これよりもグッと素敵な作品が作れます!
あなたも気軽にチャレンジしてみてくださいね(*^^*)
参考サイト:http://www.shishupub.com/paper.html
詩の歴史と有名人
詩について勉強したついでに、詩の歴史についても少しお話ししておきたいと思います。
「詩」という言葉は明治になってから使われるようになり、西洋文学の影響から作られた「新体詩抄」などが起源と言われています。それまで日本では「詩」といえば漢詩のことを指していました。
しかし「詩」という言葉こそ使われてはいませんが、文字が発明される前から韻文を朗唱したり、節をつけて歌うことが人々のなかで楽しまれており、実際はこれらが詩のはじまりとされています。
そして詩がここまで文学として確立してされてきた背景には、有名な詩人の存在があります。
ここでは有名な詩人と代表作について少し紹介しておきますね(^^)/
・中原中也
代表作:「サーカス」、「汚れちまった悲しみに……」など
・金子みすゞ
代表作:「私と小鳥と鈴と」、「大漁」など
・谷川俊太郎
代表作:「生きる」、「ことばあそびうた」など
「汚れちまった悲しみに……」や「私と小鳥と鈴と」は子供向け番組の中でメロディーがつけられ、実際に歌としてうたわれています。
また谷川俊太郎氏は詩人だけではなく、有名なところでは「スイミー」や「スヌーピー」の翻訳もされているそうですよ!「ことばあそびうた」は、私が小学生の時に教科書に載っていて「かっぱかっぱらった…」と暗唱したこともあり、とてもなじみがあります(*^^*)
あなたの知っている作品はありましたか?見聞きしたことのある作品があれば、より詩を身近に感じイメージしやすいのではないかと思います(*^^*)
夏休みや夏に関する詩を書いてみよう!盛り込む夏らしい言葉や情景とは?

さきほども少しお伝えしましたが、せっかく夏休みの宿題として詩を書くのなら、夏休みや夏をテーマとした作品を作ってみましょう♪
作品作りのヒントとなるような言葉や情景の一例を、ここではお伝えしていきますね(*^^)v
<言葉(キーワード)>
夏、夏休み、太陽、海、水着、浮き輪、川、プール、山、昆虫、
そうめん、かき氷、わらびもち、冷やし中華、ソーダ水、すいか、
盆休み、終戦日、宿題、日記、
クーラー、扇風機(せんぷうき)、団扇(うちわ)、蚊取り線香、
朝顔、向日葵(ひまわり)、麦わら帽子
<情景>
花火大会、夏祭り、盆踊り、屋台、キャンプ、バーベキュー、流しそうめん、
海水浴、川遊び、昆虫採集、田舎(いなか)への帰省、旅行、
プール開放、平和登校日、夏バテ
ほかにも夏をイメージできる言葉はたくさんあるので、思いついたときにメモしておくと詩を作るときに役立ちますよ(*^^*)ちょっとした時間をうまく使って、下準備をしておくことがオススメです!
夏休みの詩の宿題攻略法!高校生らしい俳句を作るポイントは?
詩を作るポイントは?
詩を作るといってもここまで勉強してきてわかるように、なにも難しい言葉を使う必要はありません。高校時代にしか体験できないことや、普段から疑問に思っていることを、自分の言葉で表現すればほかにないオリジナリティーのあふれる作品を作ることができます。
またテーマが浮かんだら、すぐにスマホにでもメモしておくこともオススメですよ!忙しい毎日を過ごしていると思うので、あとになって“あれ?なんだっけ?”となると時間がもったいないですよ(>_<)
大人になって読み返したときに、“あの時はこんな気持ちだったな”と思い出せるような作品を作ることを意識してみましょう。
それに加えて擬人法(ぎじんほう)や擬音語(きおんご)と擬態語(ぎたいご)の総称であるオノマトペ(擬声語)を使えば、詩の中にもっといい味が出てくるのでオススメですよ♪
・擬人法:人以外のものを人に見立てて表現すること。
例としては“風がささやく”“鳥が歌う”など
・擬音語:物が発する音や声を文字にしたもの。
例としては“ドンドン”“ワンワン”など
・擬態語:状態や心情など、音のしないものを音によって表したもの。
例としては“ドキドキ”“ニヤニヤ”“わくわく”など
親ができること
高校生にもなると親ができることは、“感想を伝える”ことのみです。とは言っても、多感期の子供が作った詩を見せてくれるとも思えませんが・・・(笑)
感想を求められたときは心のなかでガッツポーズをしながら、率直な感想を伝えてあげてください♪
ただし細かいアドバイスをすると嫌がられるリスクもあるので、ほどほどに伝えることをオススメしておきます(+_+)
参考になる!夏・夏休みに関する詩が紹介されているサイト5選!
高校生新聞
「高校生新聞」は全国の高校生に愛読されている新聞で、高校生が充実した毎日を送り、自分に合った進路を選べるようにと多くの情報を発信しています。
毎年、國學院大學と高校生新聞社が主催の「全国高校生創作コンテスト」が開催されており、短篇小説の部、現代詩の部、短歌の部、俳句の部の4部門への応募が可能です。
興味のある方は1度応募してみてはいかがでしょうか?
「時間」
九月の中旬なのに蟬が鳴く
木々が空を覆い、点々と漏れる光
私はまだ目が開かない
脳が動かない
ジャリジャリと木の実やら小枝を踏んでは
ハンカチを首元にあてる
汗ばむ背中に生暖かい風が吹く
じんわりと溶けていくようだ
誰もいない朝の教室
目を閉じて耳を澄ませば
騒がしい風景が思い浮かぶ
普段では味わえない時間
目を開けて耳を澄ませば
机に浮かび上がるカーテンの影
ノートのページが捲れる音
数々の机が教卓にいる私を威圧しているようだ
そろそろみんなが来る時間
九月の中旬なのに蟬が鳴く
こちらは高校2年生が作った作品で、第21回高校生創作コンテストで佳作を受賞した作品です。
やはり高校生にもなってくると、言葉の選び方やセンスが光ってきますよね♪
でもこちらは選ばれた作品なので、身構える必要はないですよ!(笑)こんな書き方もできるんだなと参考にしてもらえれば十分です(*^^*)
公式サイト: http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/4775
第19回ともなり文芸祭り大賞作品
栃木県矢板市で毎年開催されている“ともなり文芸祭り”の大賞作品が掲載されています。詩のほかにも短歌や川柳などの部門が年齢別に設けられているので、見ごたえがあります!
「埴輪(はにわ)」
埴輪は見ている
田畑を走り回る僕達を
腰を曲げて野良仕事をしている老人を
子どもを迎えに行く親を
産声をあげた新たな生命を
埴輪は見ていた
歴史の変革を
戦地へ赴く人々を
時代とともに
変わりゆく街並みを
汗も流さず
涙も流さず
良い日も悪い日も
顔色一つ変えず
ただただじっと見ているだけ
世界の全てを映す
ビデオカメラの映像のように
埴輪は見つめている
こちらは高校1年生が作った作品で、第19回ともなり文芸祭りの「詩」中・高生の部門の大賞受賞作品です。
どうして埴輪をテーマにしたのかがとても気になりますが、目まぐるしく変わっていく時代をいつもじっと見つめている埴輪の姿を想像することができました。
誰も選びそうもないテーマを見つけ、話を広げていく技術は真似したいものですね(*^^)v
公式サイト:http://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/syougaigakusyu/tomonari.html
公益財団法人ひろしま文化振興財団
公益財団法人ひろしま文化振興財団は地域の文化支援をしている団体で、1990年から毎年“けんみん文化祭ひろしま文芸祭”を開催しています。
「一日」
ああ一日の始まりはなんと早いのだ
朝四時目をこすりながら起きる
世間のように冷たい水で顔を洗い
母のように暖かく優しいタオルで拭きとる
まるで昨日一日の自分をなかったことにするかのように
もう日の出だ
寝起きの顔をした太陽がぽつりと顔を出してきた
浅い日の光に焼かれながら私は自転車を走らせた
バイト先のコンビニで私はレーンから流れてくる弁当箱に
そっとご飯をのせる様に優しく接客をした
バイトを終え学校へ急ぐ
そこから先はいつもの日常
ただただ勉強という魔物を頭を使って攻略する
そして帰路についた
家という当たり前のようで実はそうではない所へ
私は身を任せる
今日一日冷たい世界に身を投じ灼熱の太陽に
焼き尽くされた私の体は
まるで綺麗な机から埃の溜まった部屋の隅まで
掃除をしたボロ雑巾のようにいろいろな物を吸収していた
一日で得る物はなんと大きいのか
あと何度同じ一日を過ごすことになるのだろうか
こちらは高校3年生が作った作品で、2018年の入賞作品です。
コンビニへ早朝アルバイトに行き、学校へ行き帰宅する。自身が過ごしている毎日を比喩でうまく表現しているところがスゴイですね!
過去の作品も見られるようになっているので、時間のある時にでものぞいてみてくださいね♪
公式サイト:http://www.h-bunka.or.jp/zaidan/bungeisai/18/bungeisai.html
高校生世代「人権の詩(うた)」
島根県では毎年県内の高校生に対し、人権に対する詩を募集しています。人権に対する想いや自分の身近で起きた心温まる体験などをテーマにした作品が中心となっています。
「変わる」
「おはよう」って言えない
みんなの話についていけない
わかってる、全部私が悪いこと
ほんのちょっと勇気を出せばいい
ほんのちょっと我慢すればいい
でも、できない
「遊びにいこう」って言えない
みんなのノリについていけない
わかってる、私のせいだって
ほんのちょっと頑張って話しかけたらいい
ほんのちょっと自分に正直になればいい
でも、できない
「助けて」って言えない
みんなと同じように笑えない
わかってる、私が変わらなきゃって
ほんのちょっと頼ればいい
ほんのちょっと優しい気持ちになればいい
でも、できない
どうやったらみんなと仲良くなれるの?
どうやったらみんなと普通に話せるの?
変わりたい
そう問いかけても答えは誰も教えてくれない
だって
変わらなきゃいけないのは自分の心だから
自分の性格だから
自分で考えるの
きっといつか、変われる日を信じて
頑張れ、自分。
こちらは高校1年生が作った作品で、第4回で最優秀賞を受賞した作品です。
高校生のころって本当にいろんなことを考える時期ですよね。考えているときは本当に辛かったり、大変だったりすることも多いと思います。でもこうやって言葉にしたり、誰かに伝えたりすることで気持ちは楽になりますし、成長していくものです。
楽しいことも辛いこともたくさん経験できるのは今だけですよ!適度に肩の力を抜きながら、今しかない経験をたくさん積んでくださいね(*^^*)
公式サイト:https://www.pref.shimane.lg.jp/life/jinken/jinken/jinken_keihatu/event/otherwise/H28jinkennouta.html
サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール
「おかあさんの詩」全国コンクールは、岩手県北上市で毎年開催されています。「おかあさん」の詩を最も多く書いた詩人であるサトウハチロー氏の影響を受け、「おかあさん」をテーマにした詩を作ることで「心の教育」をしていくことを目的にしている全国規模のコンクールです。
「面会に来た母」
母が面会に来た。
入院してから
初めての面会だった。
面会室のドアが開き
とびっきり笑顔の母が入ってきた。
とても嬉しそうな顔だった。
でも苦しかった。
昔から母は
一番辛い時に一番の笑顔になる。
面会の時
母は一番の笑顔だった。
あれほど嫌だった母との会話が
とても楽しかった。
たった30分が
5分に感じた。
帰りぎわ
母と自分が
握手する。
母の手は温かく
とても「強かった」
力とか にぎる強さじゃない。
でも 強かった。
こちらは18歳が作った、第22回の入賞作品です。
思春期になると親との関係が少しぎこちなくなる人もいますよね。けれど自分が落ち込んでいるときや弱ったとき、親がいつでも子供のことを考えてくれていることに気付かされたりします。
普段は言えない感謝の気持ちを詩にしてプレゼントすれば、喜ばれること間違いなしですよ♪
公式サイト: http://www.okaasan-no-uta.jp/index.html
まとめ

詩を作るのは難しいというイメージを持っていた人も、同年代の人が作った作品を見ることで“自分でもできそうだな”と感じたのではないでしょうか?
どの作品もテーマは日常にありふれたもので、そこから内容を掘り下げていくことによってより深みのある作品となっています。高校生が詩を作るときには言葉を並べるだけではなく、 その言葉を“どう表現していくか”を意識することで味わい深い作品を作ることができますよ(*^^*)
最後になりましたが、詩を作るときのポイントをまとめておきます♪
高校生らしい詩の作り方
① 楽しい体験や思い出をたくさん作る
② 詩にする内容(テーマ)を決める
③ テーマに合った言葉(キーワード)を選ぶ
④ キーワードを含んだ短い文章を作る
⑤ 作った文章をいい感じに並べ替え、まとめる
⑥ 完成!
大人になって振り返ってみると高校時代の夏休みは学生時代のなかでも1、2を争うほど思い出深いものになっているはずです!
今しかできないことに挑戦し、楽しいことも辛いこともたくさん経験してくださいね(*^^*)
そのとき体験したことをあなたなりの言葉で表現すれば、ただの宿題だった「詩」が大切な「想い出」へと変わりますよ(*^^)v